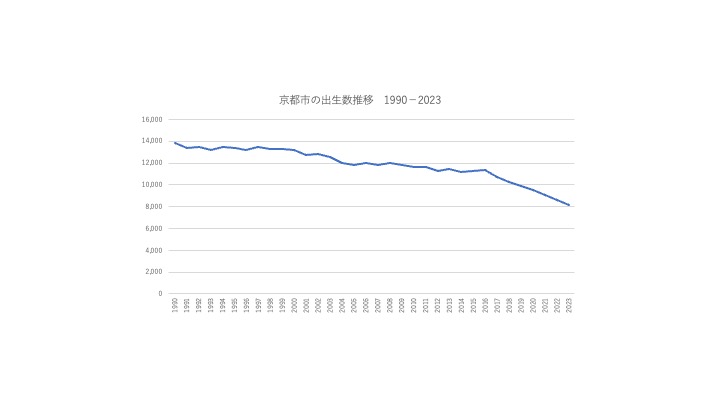https://www.keio-up.co.jp/kup/gift/bousei.html
昨年10月、ふと思い立って、パスポートを取得した。
不惑をすぎたこの年齢まで、私は海外旅行をしたことがない。学生時代までは貧しくて、海外旅行など贅沢だと諦めていた。医者になって多少は稼ぐようになったが、新生児学では博士論文は書けまいと大学院にも行かず、海外留学にも縁がなかった。
なにより時間がなかった。医者になって3年目以降、私は常に「最後の一人」であった。ラストワン・スタンバイ。当直や自宅待機番の、埋まらない最後のひとこまを埋める人。次月の当直表が確定する月末まで、個人的な事情は宙に浮かせておかねばならない立場に、私は常にあった。
それが何を思い立ってパスポートを取得しようとしたのか、今となっては思い出せない。ティモシー・スナイダー著の「暴政―20世紀の歴史に学ぶ20のレッスン」を読んで、一人前の市民たるものパスポートくらいは持っておくものだという教訓に感化されたような記憶はある。しかしそればかりではない。鬱鬱とした当直の夜、アマゾン他の通販で散財することはあった。そのときのような、これが手に入れば今度こそ現状が何か変わるかもしれないという、漠然とした期待によることだったようにも思う。
むろん実際には、これまで買った積ん読本やがらくたと同様、パスポート1冊が劇的な変化をおこしようもなく、たんに物がひとつ増えただけの日常が始まるのみではあった。それはそうなので、入手したパスポートを手にそのまま京都駅から「はるか」に乗って関空へ行ってしまったらそれは即ち身の破滅だ。
しかしパスポートを具体的な物体として手にしてみると、国外の領域がにわかに、現実の存在となったようには感じられた。それ以前は、自分の周囲の世界は遠ざかるにつれて霧の中に霞んでいって、ついに国境のあたりでかき消えていたようなものだった。パスポートを手にすることで、 霞が消えて国境が明瞭な線となり、そのむこうの世界が実体となった。物語の世界ではなく、現実に行ってみることのできる世界。となってみると、行ってみたさが募ってきた。
せめて2泊なり3泊なりだけでも、時間がとれないものか。週末の当直や自宅待機番を外し、金曜午後の予約も入れず、月曜の業務も外して。予定表をにらんでみた。11月も12月も多数の予約が入っていた。1月はどうせインフルエンザの流行が来るから休めまい。強引に休みを入れるにしても2月だと思った。
そこで2月に4日間、この日は何が何でもオフを取るぞと決意して予定表に書きこんだ。どこへ行こうと考えて、初心者向けで暖かいところにしようと思った。なら台北だ。ソウルやプサンもよかろうが(特にプサンなんて長崎の実家からは京都よりも近いんじゃないか?)、2月じゃ寒かろう。大韓民国との友好を軽んじるつもりはないが、ここは南方だ。とすれば手頃なのは台湾だ。
そこでexpediaを使って、台北への航空便とホテルの予約をとった。まず既製事実をつくって自分を追いこむのだ。そうしたのは昨年のうち。武漢ですらまだ平穏なころだった。年が明けて新型コロナウイルスが猖獗を極めるなど思いもよらなかった。1月になってもまだ私は、今年は例年のインフルエンザの流行が一向に来ないなと訝しみつつ、武漢から伝わる流行の過酷さについてはどこか他人事だった。これなら休暇は1月でもよかったじゃないかとも思ったほどだ。
南方だからというだけで選んだ旅行先であるが、行くと思うと台湾が何となく気になる。図書館で「自転車泥棒」呉明益著など読む。すぐれた文学だと思う。また、人情あふれるよい土地じゃないかと思う。近所の台湾料理屋に行ってみる。中華料理といっしょくたにしていたのが、これは全く別のものだなと思う。花の香りのする米飯など、これまでは想像の埒外でさえあったが、食べてみればうまいものだった。飽きるかと思ったが案外そうでもない。 ケーブルテレビの番組で台湾のものがあれば観る。消防署員のドキュメンタリーが今も記憶に残っている。厳しい勤務をする。あいまに皆で飯を喰い、休暇には故郷に帰る。なにかこう、だんだん台湾が世界の中でも特別に縁のある土地であるかに思えてきていた。
2月の旅行をあきらめたのがいつ頃だったか、今はもう思い出せない。2月の当直や業務配分を組む段になって、なんで過去の俺は休暇が可能だなんて思ったのだろうと頭をかかえたのは覚えている。結局、人が増えたわけではないし、自分がラストワン・スタンバイであることにかわりはない。結局、休暇など自分には無理だったということだろうと、自嘲半分に予約をキャンセルした。expediaの人が交渉してくれて、ホテル代は返金してもらえた。Peachの航空券代は無理だったが、その後の航空業界の苦境を思うと、わずかでもカンパになったと納得している。
それからすっかり旅行は無理になった。病院は職員に対する生活規制をどんどん強め、国内旅行さえ不可能になった。俺は勤め先の小児科外来を一般と発熱に分け、着慣れぬPPEを着て診療している。会食もできないと出不精に拍車がかかる。近所の台湾料理屋は早々に店を畳んでしまった。ずいぶん早い時期で、ひょっとしたら、日本の対応の拙さを早々に見切って、台湾に帰られたのかもしれないなと思った。
台湾の今回の流行対策は鮮やかな手腕であった。各論のひとつひとつが輝いて見えた。憧れはいや増すものの、観光に行ける状況ではない。まずは流行が何とかならないといけない。終戦後の大不況も耐えぬかねばならない。私自身も世の中の不況に加え、おそらく極度に悪化するだろう医療不信にも耐えねばなるまい。また台北政府にとっても、すっかり米国が経済も政治も失速し、大陸中国に一極化していくであろう壮況は、とりわけ苦境となるかもわからない。しかし管見の及ぶ範囲においてさえ大陸と明らかに異なる彼の島が、大陸に飲み込まれるのを見るのはしのびない。なんとか渡航できる日が来たときの台湾は、いま同様の華麗な姿であってほしい。
この流行に、終わりが来るのかさえまだわからない。終結への道は、はるけく遠く、台湾はさらに遠い。その日の物語が、私の人生のうちにあることを願う。